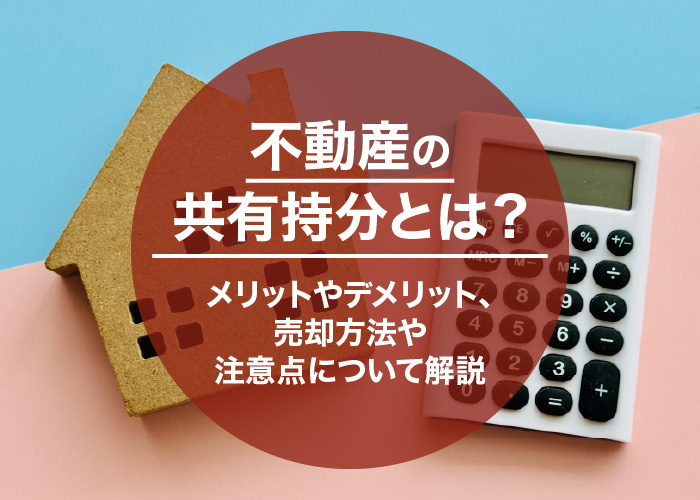
不動産の共有持分とは?メリットやデメリット、売却方法や注意点について解説
不動産を相続したものの「建物そのものではなく共有持分だった」、「どのように取り扱えば良いのかわからない」という方は少なくありません。
不動産の共有持分とは、どのような権利を指すのでしょうか。
また、取り扱いにはどのような点に注意しなければならないのでしょうか。
本記事では、
共有持分の権利や制限、メリット・デメリットや売却方法
について詳しく解説します。
不動産の共有が発生する主な原因や売却の際の注意点もご紹介しますので、相続の可能性があるという方は、ぜひお役立てください。
はりき不動産は、東京都葛飾区の不動産を中心に仲介・買取などを行っている、1970年創業の会社です。
不動産買取に関する不安点や疑問点についてはもちろん、具体的な売却の流れや費用などについてもわかりやすくご説明しますので、不動産買取を検討している方は、弊社までお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
https://www.c21hariki.com/contents/contact_info/form
不動産の「共有持分」とは?
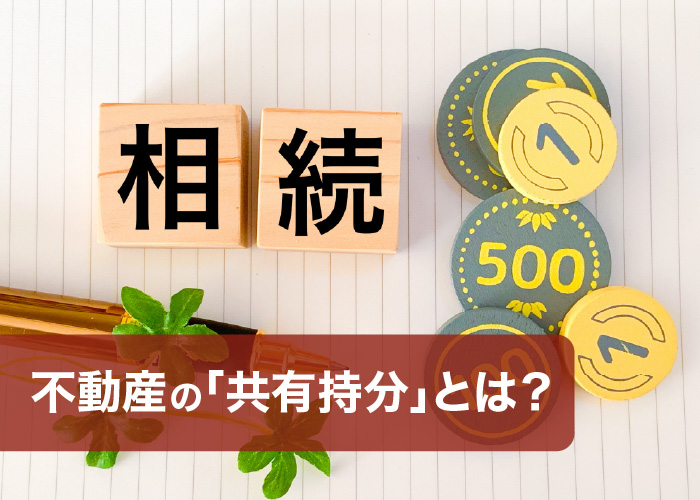
そもそも不動産の共有持分とは、一体何なのでしょうか。
また、どのようなケースで不動産を共有する事態が発生するのでしょうか。
まずは共有持分の権利と制限について詳しく解説します。
共有持分とは
一つの不動産を複数人で所有することを「共有」といい、共有している不動産の所有権の割合を「共有持分(きょうゆうもちぶん)」といいます 。不動産の共有持分の割合は、共有者の住所や氏名と共に「持分 〇分の〇」という形で登記されています。
自身の持分がわからないという方は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して確認してみましょう。
不動産の所有権は法的に対等であり、持分が1%でもあれば、99%所有している共有者とも対等に法的な権利を主張できます。
また、他の共有者が持分を放棄したり、死亡したりした場合、持分は他の共有者に帰属します。
不動産の共有が発生する主な原因
一つの不動産を複数人で共有する場合には、主に以下のようなケースが考えられます。|
・両親が亡くなって、兄弟姉妹など複数人で不動産を相続した場合
・夫婦や親子でペアローンを組んで、不動産を購入した場合 ・複数人で共同出資を行い、不動産を購入した場合 |
一つの不動産を複数人で共有するとなると、遺産分割や不動産の活用方法で揉めてしまうケースが少なくありません。
不動産の共有を避けたい場合は、上記のような状況に陥らないように注意しましょう。
共有持分の権利と制限
共有持分には、いくつかの権利と制限が設けられています。今後、相続した不動産の用途を検討する前に、権利と制限について正しく把握しておきましょう。
①共有物の使用
原則として、共有者は自身の持分に応じて不動産を自由に使用できますが、他の共有者の使用を妨害してはいけません。また、 自身の持分を超えて不動産を使用する場合は、他の共有者に対して、使用料や収益などの対価を支払う義務があります 。
三人で共有している不動産を一人が使用している場合は、他の二人に対価を支払わなければならないという点には注意が必要です。
②共有物の管理
共有持分には、不動産を利用したり、改良したりする権利も含まれます。共有している物件の改装を行う、土地の整地を行うといった行為がこれにあたり、共有者の持分価格のうち過半数の同意があれば実行できます 。
第三者に賃貸したり、賃料の決定や変更を行ったりすることも可能で、他の共有者の所在が不明である場合でも、裁判所の許可があれば管理行為が可能です。
③共有物の変更・処分
共有物の変更とは、増改築で不動産の形状を大きく変更したり、不動産を取り壊して法的に処分したりする行為を指します。軽微な変更であれば共有者の持分価格の過半数で決定できますが、大きく変更を行う場合には、共有者全員の同意が必要であるという点には注意が必要です 。
ただし、「共有物の管理」と同様に、他の共有者の所在が不明である場合には、裁判所の許可があれば実行できます。
④持分の譲渡・担保設定
共有持分の権利には、第三者への譲渡や担保設定も含まれます。自身の共有持分だけを譲渡したり、担保に入れたりする行為は、他の共有者の同意がなくとも自由に行えます 。
自身の共有持分全体に抵当権を設定することは可能ですが、共有持分をさらに分割して「一部分のみ」に設定することはできません。
単独名義の不動産であっても、抵当権を設定できるのは「不動産所有権の全体に対して」であるという点には注意が必要です。
はりき不動産では、共有不動産である建物や土地も取り扱っております。
不動産の共有持分を相続したものの「取り扱いに困っている」、「手放す方法がわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはこちら
https://www.c21hariki.com/contents/contact_info/form
共有持分のメリット

共有持分のメリット
権利が複雑化することから敬遠されがちな共有持分ですが、メリットもたくさんあります。具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。詳しく見てみましょう。
ローンが組みやすくなる
一つの不動産を複数人で共有することで、「ローンを組みやすくなる」というメリットがあります。単独で借り入れを行う場合、一人分の収入や債務状況で審査が行われますが、複数人で借り入れを行う場合、全員分の収入や債務状況が審査対象となります。
そのため、単独でローンを組むよりも、借入可能額を増やせるという点は大きな魅力だといえるでしょう 。
単独では購入が難しい高額な不動産でも、共同名義にすることで購入できる可能性があります。
税金や管理維持費を抑えられる
複数人で不動産を所有することで、税金や管理費を抑えられるという点も大きなメリットだといえるでしょう。不動産を所有すると、利用していなくても固定資産税や修繕・補修などの管理維持費が発生します。
単独で全ての費用を負担するよりも、複数人で負担した方が、一人あたりの支払額は少なくなります 。
不動産の規模が大きくなるほど、税金や管理維持費の負担も増えるため、複数人で共同所有するというケースも少なくありません。
住宅ローン控除が受けられる
複数人で不動産を購入すると、住宅ローン控除が二重に適用される可能性があるという点も魅力だといえるでしょう。住宅を単独で購入すると、適用される住宅ローン控除は一人分です。
しかし、 夫婦や親子でペアローンや連帯債務型ローンを組んで購入すると、二人分の住宅ローン控除が適用されます 。
ただし、連帯債務型ローンの場合は、住宅ローン控除が二重に適用されない可能性があるので、事前に金融機関へ確認しておいてください。
共有持分のデメリット

メリットが多い共有持分ですが、当然デメリットも存在します。
共有持分を保有している、相続したという方は、デメリットについても正しく把握しておきましょう。
自己判断で不動産を活用できない
共有持分にはさまざまな権利が認められていますが、管理や変更・処分を行いたい場合は、共有者の同意が欠かせないという点はデメリットだといえるでしょう。賃貸に出したり、大掛かりなリフォームを行ったりしたいと思っても、他の共有者の賛同が得られない場合は実行することができません 。
また、共有不動産は権利が複雑であり、運用の自由度が低いため、手放すことも難しいという点には注意が必要です。
相続によって権利関係が複雑化する
不動産の共有者が増えるほどに権利関係が複雑化するという点もまた、共有持分のデメリットの一つです。共有者の一人が亡くなって相続が発生したときに相続人が複数いる場合、持分がさらに細分化して共有者が増えることになります。
共有者が増加すれば、その分、管理や変更・処分を行う際に同意を得られにくくなるという点には注意が必要です 。
顔も知らない遠縁の親族と争うことになるケースもあるので、権利関係の複雑化を避けたい場合には、単独名義で不動産を相続するか、共有者の数を可能な限り減らしておいた方が良いでしょう。
共有持分の不動産は売却できる?
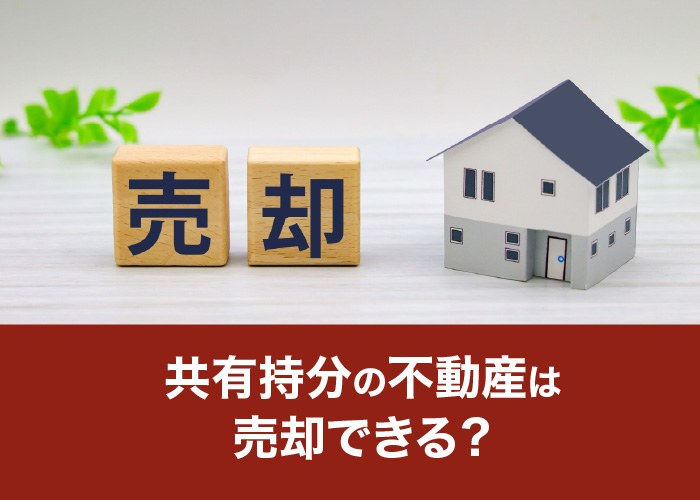
デメリットを知って、共有持分を手放すことを検討している方もいるでしょう。
取り扱いが難しい共有持分は、一般的な不動産と同じように売却できるのでしょうか。
共有持分は自由に売却できる
不動産を複数人で共有している場合でも、自身の共有持分は自由に売却することが可能です。他の共有者の同意は不要であることから、自身の判断で売却の手続きを進めても問題はありません 。
ただし、共有持分を売却せずに放棄する場合は、「所有権移転登記」の手続きが必要です。
共有持分を放棄すると他の共有者に権利が移るため、同意を得た上で手続きに協力してもらう必要があります。
また、所有権移転登記の手続きを行うと、贈与とみなされて「贈与税」が課税されるという点には注意が必要です。
不動産会社に買取を依頼する
自身の共有持分を売却したい場合は、専門性の高い不動産会社に買取を依頼しましょう。共有持分は不動産活用の自由度が低いことから、買取を拒否する業者も少なくありません。
また、自由に売却できる権利を持っていたとしても、他の共有者が売却に反対してトラブルにつながるケースもあります。
共有不動産の売却は簡単ではないので、共有持分の取り扱いに慣れている不動産会社を探すことが大切です 。
万が一、トラブルに発展した場合を想定して、法律や税務に関する知識にも明るい不動産会社に買取を依頼することをおすすめします。
はりき不動産では、共有持分の不動産の仲介や買取も行っております。
「共有不動産の持分を売却したいけれど、他の共有者との交渉が難航している」、「他の不動産会社から、共有持分の不動産は買取できないと言われた」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはこちら
https://www.c21hariki.com/bai_contact/bai_assess/form
共有持分の不動産の売却方法と注意点
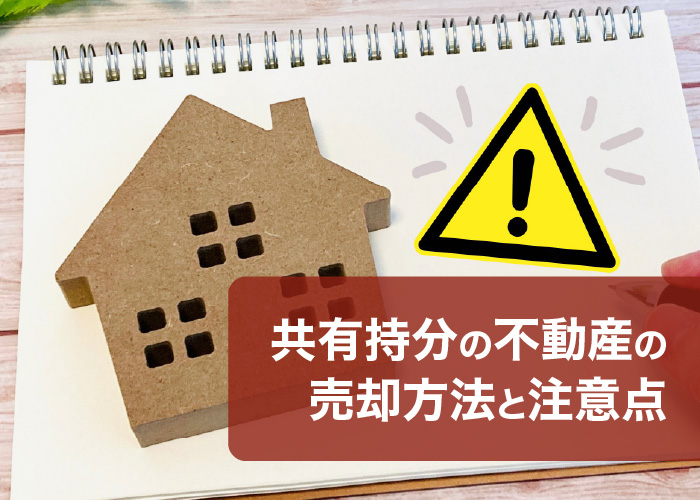
共有不動産は、不動産会社に買取を依頼することで売却できます。
しかし、他にも共有不動産ならではの売却手段がいくつか存在します。 最後に、共有持分の代表的な売却方法を三つご紹介します。
売却方法①他の共有者に自身の持分を売却する
共有持分の売却を思いついた場合は、まず他の共有者に買取を打診してみましょう。買取を快く受け入れてもらえれば、スムーズに売却できる上に権利関係がシンプルになり、お互いにとってメリットの多い解決策となります 。
共有者が一人しかいない場合は、単独名義となって不動産の活用の幅が広がるため、喜んで買取してもらえる可能性があります。
ただし、個人間で不動産売買に関する契約を結ぶとなると、後々トラブルに発展するケースもあります。
揉め事が起こらないように、契約の際には不動産会社に間に入ってもらうと良いでしょう。
手数料はかかるものの、不動産契約に詳しい第三者に間を取り持ってもらうことで、不要なトラブルを避けられるというメリットがあります。
売却方法②共有者全員で第三者に売却する
自身の共有持分だけでなく、他の共有者も不動産を手放したいと考えている場合は、全員で協力して第三者に売却すると良いでしょう。全員が売却に同意している場合は、スムーズに手続きを進めることができます。
持分だけを売却すると、市場価値よりも売却価格が下がってしまう可能性がありますが、一つの不動産を丸ごと売却すれば、市場価値相応の価格で売却できます 。
共有者がそれぞれ売却の手続きを行うよりもお得なので、売却を検討している方は、他の共有者の意見や考えを聞いてみると良いでしょう。
売却方法③分筆して売却する(土地のみ可能)
共有不動産が一定の広さがある土地の場合は、事前に分筆して売却するという方法もあります。分筆とは、一つの土地を複数の土地に分割して登記を行い、共有者がそれぞれ単独で所有することを指します 。
土地を単独名義で所有できることから分筆を希望される方も少なくありませんが、持分に応じて単純に土地を分割することは難しいといえるでしょう。
二人の所有者が土地を半分に分け合ったとしても、土地の価値を平等に分け合えるとは限りません。
方角や日当たりによって土地の価値は異なるため、持分に応じて分け合ったとしても、公平性を保つことが難しいのです。
どのように分筆すれば良いのかわからないという方は、不動産会社に相談しましょう。
他の解決策を提示してもらえる可能性もあるので、共有者間でのトラブルを避けるためにも、第三者である不動産会社に間に入ってもらえると安心です。
まとめ
権利関係が複雑で簡単には売却できないというネガティブな印象を持つ共有不動産ですが、不動産会社によっては、親身になって仲介や買取の相談に乗ってもらえます。
共有持分を持て余している、取り扱いに困っているという方は、共有不動産の買取に慣れている不動産会社を頼りましょう。
「所有している共有不動産の売却を希望している」、「どの程度の額で買取してもらえるか知りたい」という方は、まずは不動産会社へご相談ください。
1970年創業のはりき不動産は、東京都葛飾区に精通した地域密着型の不動産会社です。
住み替えや離婚、相続など、さまざまな理由での不動産売却に対応可能
です
。
不動産を高く売却するための弊社オリジナルの5つの方法をもとに、高値での査定を実現しております
。
葛飾区で土地や物件の買取を依頼できる不動産会社をお探しの方は、ぜひはりき不動産へご相談ください。
お問い合わせはこちら
https://www.c21hariki.com/contents/contact_info/form